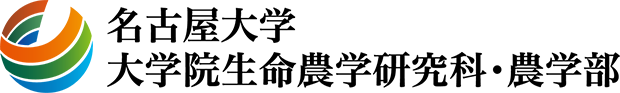大学の施設としては、
リサーチセンター
http://www.research.uwa.edu.au/list-of-centres#ric
図書館
https://www.uwa.edu.au/library/home
宿舎
https://study.uwa.edu.au/student-life/accommodation/live-on-campus
など、本プログラムの学生が副大学であるUWAに移動後、比較的短時間で現地の研究に溶け込みやすい環境があります。また研究面をみますと、名古屋大学大学院生命農学研究科は基礎研究に力を入れつつ最先端の研究を行っていますが、西オーストラリア大学は基本的な’発見による’研究、そして社会との強い連携を持って行う応用研究でその存在感を示しています。